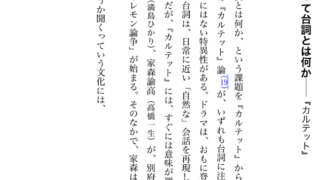 blog
blog 藤田真文先生の『テレビドラマ研究の教科書』、あるいは、カルチャー研究の入門書はもっとやさしくしてください
学部学科の事情で、私のゼミ(演習)にはカルチャー関係の卒論書きたい学生様も来るわけですが、私はそういうのの専門家じゃないのでいろいろ苦労してるんですわ。一番苦労するには、学生様が読むべきだと思われる本や文献を探すことですね。専門に近いところ...
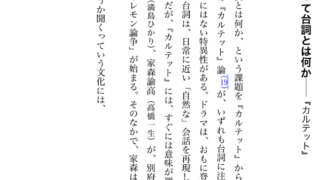 blog
blog  お説教
お説教  教員生活
教員生活